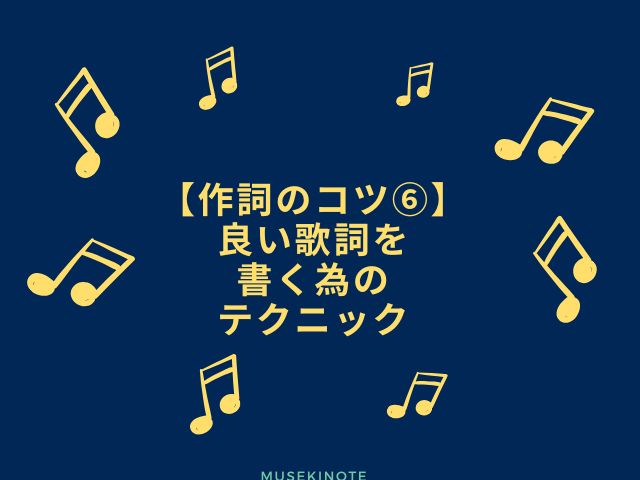
良い歌詞を書く為のテクニック
こんにちは、ムセキ(@nagoyakampo)です。趣味で作曲をしていて、過去には市販されているゲームに曲が採用されたこともあります。
今は、歌の無いインストゥルメンタルを中心に作曲していますが、過去にはボカロ曲等、歌詞のある曲を作っていました(サブスク配信、ゲーム内の曲としての採用実績もあります)。
歌のある曲にする為には、オーケストレーション(オケ)だけではなく歌詞も必要です。歌詞を書く「作詞」は、「作曲」とはまた違った難しさやコツがあります。
作詞について、自分自身はボカロ曲を作るまでは全く触ったことが無く、色々と調べて苦労しました。
ですので、まとまった情報があると同じ様に困っている方のお役に立てると思い、本記事を書くことにしました。
本記事の内容は「良い歌詞を書く為のテクニック」で、以下の構成になっています。
曲のイメージに合う言葉を使う
ストーリーを意識する
シンプルな言葉を心掛ける
感情に訴える英語を取り入れる
創造的な言葉を使う
サビ冒頭では「あ、い、え」
キーとなる言葉を繰り返す
韻を踏む
推敲する
さいごに
作詞は自分自身を全て出して行うクリエイティブな作業ですが、幾つかコツを意識して作っていくと、より良い歌詞にすることが出来ます。
本記事では、僕が作詞をする時に気を付けている「作詞のテクニック」をご紹介しています。是非、真似してみてください。
少しでもお役に立てたら嬉しいです。それではご覧ください。
スポンサーリンク
曲のイメージに合う言葉を使う

歌詞の完成度を上げるには、曲のイメージと合う作詞をする必要があります。まずは曲のイメージを書き出して、どんな歌詞にするかを確定させましょう。
また、曲以外にも日常の中からインスピレーションを見つけることも重要です。日記を書いたり、他のアート作品に触れたりすることで、新しいアイデアが浮かびやすくなります。
以下の記事にて、イメージの膨らませ方を詳しく解説しています。是非ご覧ください。
-

-
【作詞のコツ④】歌詞のイメージを膨らまる方法
ストーリーを意識する

曲全体を通じて一つの物語を語るようにすると、聴き手の興味を引きやすくなります。イントロからクライマックス、そして結末まで、ストーリーの流れを大切にしましょう。
ストーリーを意識した歌詞を書くには、大まかにセクションごとに歌詞の流れを決めて譜割りに書いておくと良いでしょう。
そうすることで、効率よくストーリーに沿った歌詞がかけるようになります。他にも、効率よく歌詞を書く方法は、
-

-
【作詞のコツ⑤】作詞を楽にするポイント。
にて詳しく解説しています。是非ご覧ください。
シンプルな言葉を心掛ける

複雑な言葉やフレーズを使うよりも、シンプルで覚えやすい言葉を選ぶと、聴き手にとって親しみやすくなります。わかりやすい表現を心がけましょう。
歌詞に使う言葉をシンプルにする理由には、以下のようなものがあります。
理解しやすさ
シンプルな言葉を使うことで、聴衆が歌詞をすぐに理解しやすくなります。複雑な表現よりも、わかりやすい言葉の方がメッセージが明確に伝わります。
共感しやすさ
簡潔でシンプルな言葉は、多くの人に共感されやすくなります。誰もが日常的に使う言葉を使うことで、聴衆との距離が縮まり、より親しみやすくなります。
キャッチーさ
短いフレーズや簡潔な言葉は、頭に残りやすく、リピートしやすいものになります。キャッチーな歌詞は、曲の魅力を増す重要な要素です。
感情の伝達
シンプルな言葉は、複雑な言葉以上に直接的に感情を伝えることができます。短くて強い表現は、聴衆の心に響きやすいです。
リズムとフローの適応シンプルな言葉は、リズムやメロディに合わせやすくなります。リズミカルで自然な流れを作るのに役立ちます。
創造的な余地
シンプルな言葉を使うことで、余計な複雑さを省き、創造的な表現やアイデアに集中できます。これにより、より独自のスタイルを作り出すことが可能です。
感情に訴える

歌詞には感情を込めることが大切です。自分が感じたままを素直に表現することで、聴き手にも共感してもらいやすくなります。
歌というものは、元々曲自体が感情を動かす力があります。その力を具現化するのが歌詞であり、歌声になります。
曲の盛り上がりに合わせて、歌詞に使う言葉も感情の度合いを調節すると、より効果的になります。
英語を取り入れる

日本のポップスやロックをはじめとした歌には、歌詞内に英語が部分的に使われています。漢字で歌詞を書き、英語でルビを振るというテクニックも使われています。
歌詞に英語を混ぜることで、以下のようなメリットがあります。
キャッチーな響き
英語のフレーズや言葉は、日本語とは異なるリズムや響きを持っています。そのため、英語の要素を取り入れることで、曲がよりキャッチーで覚えやすくなることがあります。
クリエイティブな表現
英語には多くのスラングやイディオムが存在し、それを使うことで歌詞にクリエイティブな要素を加えることができます。
新しい言葉の組み合わせや表現方法を試すことで、より斬新な歌詞が作れます。
また、英語は日本語のような情緒感は少なく、理論的・理知的な響きを多く持ちます。その為、歌詞内にそれらの言葉があることで、クールな印象をリスナーに与えることが出来ます。
トレンドの反映
現在の音楽業界では、英語のフレーズや言葉を取り入れた楽曲が多く存在します。これにより、現代のトレンドやスタイルを反映させることができ、リスナーに親しみやすい印象を与えます。
感情的なインパクト
英語の特定の言葉やフレーズには強い感情を伝える力があります。これを利用することで、歌詞により感動的な要素を加えることができます。
創造的な言葉を使う

歌詞に詩的な創造性豊かな言葉を使うことには、歌詞のクオリティを上げるメリットがあります。以下にその主要な点を挙げてみます。
深みと豊かさの付加
詩的な表現は、歌詞に深みと豊かさを与えます。これにより、聴衆に感動を与えるだけでなく、曲全体がより魅力的になります。
記憶に残りやすい
創造的でユニークな表現は、聴衆の記憶に残りやすくなります。特に印象的なフレーズや比喩は、曲を聴いた後も頭に残り、何度も聴きたくなる要因となります。
感情の表現
詩的な言葉を使うことで、感情をより強く、繊細に伝えることができます。これは聴衆との感情的なつながりを強化するために重要です。
視覚的なイメージの創出
創造的な言葉や比喩を使うことで、視覚的なイメージを聴衆に与えることができます。これにより、聴衆は歌詞を通じて具体的な場面や情景を想像しやすくなります。
独自性の確立
詩的で創造的な表現を使うことで、他の楽曲との差別化が図れます。独自のスタイルやサウンドを持つことで、アーティストとしてのアイデンティティを強化できます。
リズムとメロディの融合
創造的な言葉は、リズムやメロディと調和しやすくなります。詩的な表現は音の響きやリズム感を強化し、曲全体の流れをスムーズにする効果があります。
サビ冒頭では「あ、い、え」

これは日本独特かもしれませんが、サビ冒頭部分では、「あ、い、え」などの母音が多く入る言葉を使用すると効果的です。
「あ、い、え」という母音は、「う、お」の母音に比べて明るい響きがあります。特に、「あ、い」の母音を中心に使用すると良いでしょう。
これら明るい響きの母音を使うと、サビ冒頭という一番盛り上がる部分を印象強くリスナーに伝えることが出来、記憶に残りやすくなります。
キーとなる言葉を繰り返す

歌詞にキーワードを繰り返し入れることで、曲にキャッチーさが生まれます。同じフレーズやリフレインを効果的に使うことで、聴き手の記憶に残りやすくなります。
他にも、以下のようなメリットがあります。
テーマの強調
繰り返し使われるキーワードは、曲のテーマやメッセージを強調する役割を果たします。これにより、聴衆に対して曲の主題がより明確に伝わります。
感情の喚起
キーワードを繰り返すことで、その言葉に込められた感情が強調されます。特定の言葉やフレーズを繰り返すことで、聴衆の感情を引き込む効果があります。
リズムとフローの強化
繰り返し使われるキーワードは、曲のリズムやフローを整える役割を果たします。リフレインやコーラス部分で同じ言葉を繰り返すことで、曲全体の統一感が生まれます。
韻を踏む

リズムとメロディの強調
韻を踏むことで、歌詞がリズムやメロディに自然に合いやすくなります。これにより、曲全体の流れがスムーズで心地よいものになります。
聴覚的な魅力
韻を踏むことで、言葉の響きが美しくなり、聴覚的な魅力が増します。これは聴衆にとっての楽しさや興味を引きつける要因となります。
記憶に残りやすい
韻を踏んだフレーズは、聴衆にとって覚えやすくなります。これにより、曲が長く記憶に残り、何度も聴きたくなる効果があります。
統一感の提供
韻を踏むことは、歌詞全体に統一感をもたらします。これにより、曲の一貫性が保たれ、まとまりのある作品に仕上がります。
創造性の発揮
韻を踏むことで、言葉遊びや比喩を駆使した創造的な表現が可能になります。これにより、歌詞がより魅力的で個性的なものとなります。
推敲する

歌詞が出来上がった時、どんな気持ちになるでしょうか。出来上がった嬉しさで舞い上がった気持ちになるはずです。ですが、そこが落とし穴です。
その歌詞をそのまま完成としてしまうと、細かなミスに気付かず失敗します。
ですので、それを防ぐために一日程度時間を置いて、落ち着いた気分で歌詞を見返して推敲することが大切です。ボーカロイド等に歌ってもらっても良いでしょう。
そうして、書き上げた歌詞をブラッシュアップしていくと、より完成度の高い歌詞になっていきます。
さいごに

今回は、作詞講座第六回目ということで「良い歌詞を書く方法」についてお話ししました。
本記事でご紹介した通り、良い歌詞を書く方法にはテクニックがあります。そのテクニックを学ぶことで、より良い歌詞が書けるようになります。
本記事でご紹介した方法が、貴方の作詞作業の手助けになれば幸いです。それでは、ムセキでした。
「作詞のコツ」まとめ記事は、以下のリンクからどうぞ。
-

-
【歌詞の書き方】作詞のコツまとめ【初心者講座】