
基本のベタ打ちについて
こんにちは、ムセキ(@nagoyakampo)です。
趣味で作曲をしていて、過去にはボカロ曲が市販されているゲームに曲が採用されたこともあります(PSP「初音ミク -Project DIVA-」の「猫なキミ」:774P名義)。
また、サブスク等でボカロ曲を配信しています(774P名義)。
今は歌の無いインストゥルメンタルを中心に作曲していますが、昔自分がやっていたボカロ調声について、方法などを詳しく書いておこうと思い立ちました。
基本的に、ボカロ曲は「ベタ打ち」と呼ばれるものが多いのですが、そのベタ打ちはボカロ調声の基本中の基本になります。
曲によってはベタ打ちの方が良いものもあり、調声をするかどうかの判断もベタ打ちが終わってからすることもあります。
とりあえずはその基本を押さえてから、コントロールパラメーター等をいじるという順番になります。
今回の記事の内容は、「ベタ打ちの方法」です。
ネットで検索しますと「ベタ打ち脱却」等の記事やnoteがありますが、それはベタ打ちをマスターしてからの話になります。
ですので、先に本記事をじっくり読まれることをお勧めします。以下の順番でご紹介しています。
Vocaloid3 Editorの使い方について
ベタ打ちって何?
ベタ打ち全体の流れ
シンガーを決める
音符(ノート)&歌詞の入力
再生して確認
音符や歌詞の修正
エクスポート
さいごに
僕はVocaloid3 Editorを使用していますので、それを使ってベタ打ちの解説をしていきます。
ですが、基本中の基本というものあり、バージョンの違うVocaloid EditorやPiapro Studio等でも適応できます(Vocaloid Editorの1~3とPiapro Studioの使用経験があります)。
少しでもお役に立てたら嬉しいです。それでは、お読みください。
スポンサーリンク
Vocaloid3 Editorの使い方について

最初に、Vocaloid Editorの使い方についてですが、本記事では「既に基本的な使い方は問題ない。」という前提でお話ししていきます(使い方だけでも、一記事の分量になってしまいます)。
Vocaloid Editorの基本的な使い方に不安がある方は、以下の記事を先にご覧下さい。基本的な使い方をご紹介しています。
-
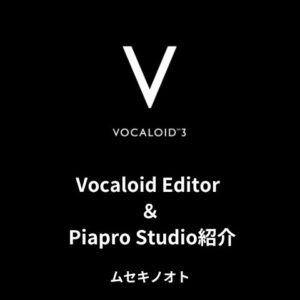
-
【ボカロ調声のコツ&テクニック①】Vocaloid Editor & Piapro Studio紹介【ボーカロイド】
ベタ打ちって何?

最初に、ボカロ調声の基本である「ベタ打ち」をご紹介します。
そもそも「ベタ打ち」という名前は初音ミクをはじめとするボカロが流行り出して、自然発生的に生まれた言葉で、意味はきちんと定義はされていません。
ですが、おおよそ「音符を入力して、そのまま歌詞を入れて終わったボカロ調声」という意味で使われることが多いようです。
語源は「ベタな」という形容詞で、「ありきたり」「そのまま」「工夫をなにもしていない」といった意味です。
ボカロ調声の「ベタ打ち」という言葉に限っては、「(パラメーター調整等の)工夫をせずにそのまま」という意味で取れば良いでしょう。
ベタ打ち全体の流れ

ベタ打ちの流れをご紹介します。ベタ打ちは土台から作業を始めていく流れが基本となります。ですが、たまに色々な理由で順序が反対になることもあります。
とりあえず、先ずは基本をご紹介します。
おおよそですが、ベタ打ちの流れは以下のようになります。
①シンガーを決める
②音符(ノート)&歌詞の入力
③再生して確認
④音符や歌詞の修正
⑤エクスポート
それでは、次の段落から個別に説明していきます。
シンガーを決める

まず、どんなボカロ調声でもそうですがシンガーを決めます。
Vocaloid EditorのMusical Editor画面でマウス右クリックをすると、項目の中に「歌手」というのがありますので、そこから選びましょう。
その時点で気に入った声が無ければ、Vocaloid Editorのアクティブシンガープロパティからパラメーターをいじって調節します。
各種コントロールパラメーターについては、
-

-
【ボカロ調声のコツ&テクニック②】コントロールパラメーター解説【Vocaloid Editor & Piapro Studio】
にて詳しく解説しています。是非ご覧ください。
音符(ノート)&歌詞の入力

シンガーが決定したら、次に音符と歌詞を入力していきます。
音符の入力に関してですが、Vocaloidは推奨される音程の範囲が決められています。それを超えた場合は耳障りな歌声になってしまうことが殆どです。
その場合はメロディを変えるか調性(キー)を変更するかのどちらかしかありません。
それを防ぐため、メロディを作る時に歌いやすいキーを最初に設定しておくと良いでしょう。
僕のお勧めは女性シンガーならF(ヘ長調/ヘ短調)~G(ト長調~ト短調)、男性シンガーならB♭(変ロ長調/変ヘ短調)~C(ハ長調/ハ短調)です。
低めの調性を選ぶとサビ部分で耳障りな声になり難いのでオススメです。
また、歌詞と音符は、Vocaloid Editorに入力するまで、自分で「文字数もピッタリ合っている。」と思っても、何かしらのミスが発見されることが殆どです。
ですので、一気には入れずに、例えば2~4小節単位で少しずつJOBメニューの「歌詞の流し込み」で入力していくのが良いでしょう。
歌詞を入力していく時のコツですが、実際に自分で声に出しながら入力するとミスが少なくなります。
これは日本語の問題ですが、目で入れた歌詞の情報と声に出した場合の音が違うことがある為です。
詳しくは、
-
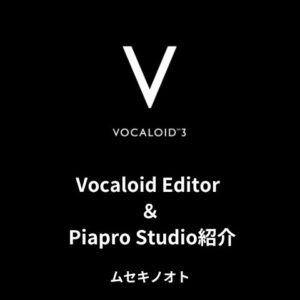
-
【ボカロ調声のコツ&テクニック①】Vocaloid Editor & Piapro Studio紹介【ボーカロイド】
の歌詞入力部分をご覧ください。
再生して確認

音符と歌詞の入力が終わりましたら、再生して聴いてみましょう。
きちんと再生出来ていると良いのですが、変なポルタメント(音符間の滑らかな音程変化)がかかったり、発音時間が想定より短くなってしまったりと上手くいかないことも出てきます。
その場合、音符か歌詞のどちらかを修正する必要があります。修正については、次の段落で詳しくご紹介します。
音符や歌詞の修正

再生して音符と歌詞の入力チェックをすると、発声が正しく出来ていなかったりポルタメントのかかり方がおかしかったりする部分があることに気がつきます。
それらを、一つ一つ修正していきしょう。以下に、よくある修正ポイントについてご紹介します。
これらの修正を行って、また再生して確認して、修正して・・・というのを繰り返して、良い歌声になるようにします。
歌詞の打ち込み修正
特に助詞や母音を伸ばす場合に起こるミスです。
-
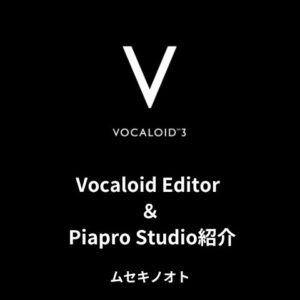
-
【ボカロ調声のコツ&テクニック①】Vocaloid Editor & Piapro Studio紹介【ボーカロイド】
でもご紹介していますが、「~は」「~へ」等の助詞は、発声する場合「~わ」「~え」と発音します。
また、「行こう」等の母音を伸ばす場合は「いこお」若しくは「いこー」と入力する必要があります。
歌詞の流し込み時に修正するのですが、主に修正忘れでミスが起こっています。これらの部分を探して、入力を修正します。
子音と母音の分割
Vocaloidの弱い所で、上手く発音がされない場合があります(特にか行・さ行・た行に多い)。その場合、子音部分と母音部分を分割すると改善する場合があります。
子音部分を16~32分音符にして、残りを母音または「ー」に置き換える等してみると良いでしょう。
母音の分割
シンガーが、指定した長さまで発音しない場合もあります。
その場合、上記のように子音と母音を分割をした後、対象の音符最後の母音部分をさらに分割してみると良いでしょう。例えば、音符最後の部分32分音符を分割してみる等です。
「n」を入れる
発音改善目的で、子音部分の直前に「n」を入れるという方法があります。意外と、これで発音が改善する場合があります。
この場合、nが目立たないようにパラメーター等を使って調整してあげると良いでしょう。
音符を削る
主に早いフレーズで発声が悪くなっている場合、音符の長さを削って少し短くしてやると、発声が改善する場合があります。
平仮名の代用
正しく発音しない場合、平仮名を代用するという方法もあります。例えば「て」の発音が上手くいかない場合、64分音符で「と」を入れて母音部分を「え」で伸ばすという方法があります。
正しくは「とぇ」発音しているので少し違和感は残りますが、早いフレーズであったり伴奏に混ぜたりすると解らなくなる場合もあるので、使い方勝負になります。
別トラックを重ねる
音符の分割や「n」をいれる、音符を削る、平仮名の代用等の方法で発音が改善しない場合、別トラックで子音部分のみを発音しうっすら重ねるという方法があります。
DYN等を使用し、重ねる方の音量を下げるのがコツです。聴きながら、一番いい値を探っていきましょう。
音量のばらつきを修正する
特定の音符だけ妙に発声が大きい若しくは小さい場合があります。その場合、コントロールパラメーターでDYNを削るか、エクスポート後にDAW側で編集します。
エクスポート

自分自身が納得行くまで歌声の修正が出来たら、WAVファイルを書き出してDAW側で作業します。DAW側で作業しやすいよう、基本的にはパート毎に出します。
ですが、発音改善目的で別トラックを使っている場合は、そのトラックはメイントラックにまとめて出した方が良いでしょう。
さいごに

今回は、ボカロ調声の基本である「ベタ打ち」についての解説でした。
ボカロ調声は色々と種類がありますが、まずは基本のベタ打ちをマスターする所が出発点になります。今回の記事が、少しでも作業のお役に立てれば幸いです。
最後にお知らせですが、本記事を含むボカロ調声記事のまとめが出来ました。以下からリンクしていますので、是非ご覧ください。
-

-
【Vocaloid】ボカロ調声のコツ&テクニックまとめ【ボーカロイド】
それでは、ムセキでした。